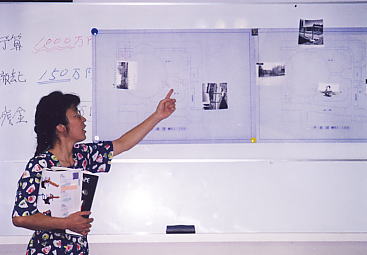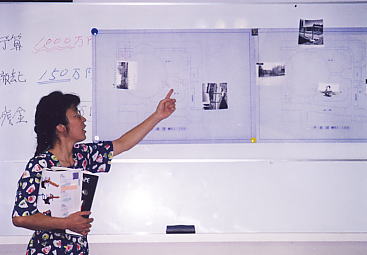実現しました!! 市民参加の公園づくり (1998年9月議会での提案)
最少の経費で最大の効果を目指し、市民自治によるまちづくりの原点を創る
実現への道のり
1996年に市議会議員となり、建設水道常任委員会の委員として2年間決算・予算を見ながら、何とかしたいと思ってきたのが、公園の遊具改修等についてでした。
館地区の4つの児童公園と館近隣公園(中央公園)は、志木ニュータウン建設に際し鹿島建設から無償譲渡されたものですが、数年前からコンビネーション遊具(太い柱を組み合わせたタイプのもの)が一斉に老朽化の時期を迎え、毎年間題になってきました。
補修といっても柱一本に数十万円もの費用がかかりますし、外見で予測できない危険も伴います。
1997年度には館第2児童公園(9,796,500円)、1998年度には館近隣公園(6,825,000円)に新しいコンビネーション遊具が設置されましたが、館第2児童公園(幸福の森幼稚園に隣接)の遊具については「色が原色できつすぎる」等近隣住民からの苦情も寄せられました。
「公園全てに当初と同様の高価な遊具でなく、“はらっぱ公園” “木のぼり公園”など特徴を持たせてもいいのではないか。」との私の意見も、所詮1人の意見に過ぎませんでした。
きっかけは一人の声から
1998年1月雪の積もる公園で、近所のOさんから「館第4児童公園(柳瀬川図書館横)のコンビネーション遊具の一部が壊れ、自分で治そうと試みたけれど、全体的に危ないようだ。」私も公園を巡る諸課題を話しました。
Oさんは、「立派なコンビ遊具を皆が望んでいるとは限らない。幼児には簡単なすべり台やブランコの方が遊びやすいのでは?」その声に刺激され、早速、みどりのまちづくり課と市内公園めぐりをしました。
市内の公園は都市公園 14箇所(市が用地を所有)
児童遊園地 37箇所(借地+市有)
市民1人当たりの公園面積は 1.7㎡で、県内でも狭い方です。
昨年策定された子育ていろはプラン(児童育成計画)のためのアンケート調査では、住宅密集地の本町地区を中心に、「子どもたちが安心して遊べる公園を」の声が多く出されました。
望ましい公園のあり方は?
公園を視察見学してわかったことは、児童遊園地は面積も狭く、すべり台・ブランコ・鉄棒といった3点セットが主体である。
館地区では、全てが当初と同じようなコンビネーション遊具主体の公園でいいのか? 高齢化の進展と共に、バリアフリーも含め、あらゆる市民が憩い、安らげる公園のあり方を皆で考えていきたいと思いました。
みどりのまちづくり課と話し合いを重ね、1998年9月の議会で「市民参加の公園づくり」について提案しました。
都市計画マスタープラン策定に向けた1997年4月「市民参加とまちづくり」講演会では早稲田大学の卯月盛夫先生から世田谷区での市民参加の公園づくりで、「参加した住民が近隣住民に聞きとり調査をしたり、最初に予算を明らかにし、その中で住民同志議論しながらデザインをした実例」を学び、是非志木市でも実現したかったのです。
「参加をすると、それに対する愛情とか愛着が高まるといわれています。そういうプロセスがないと、公共施設破壊など、結局は行政の税金の無駄遣いになってしまう。」
そして、今年度改修予定の館第4児童公園で、やってみることになりました。
館第4児童公園(柳瀬川図書館横)遊具改修について
当公園利用者を中心に公園への掲示で参加を募り、近隣の東の森1,2番街には町内会により回覧
1回目(5月25日)
1,000万円の予算内で遊具改修を行うにあたり、公園利用者及び近隣住民の意見を反映することを説明。自由に意見交換。
今回は遊具の改修ということだったが、他にも水飲み場や日よけ・ベンチ等について意見要望が出され、1,000万円の予算の範囲内で公園全体を視野に入れて考えていくこととなる。
2回目に向けて
・さらに多くの市民の意見を聞くためのアンケート(40枚)を参加者が中心になって集めた。
・2回目さらに多くの参加を募るための広報も、参加者が自主的に行った。
2回目(6月29日)ワークショップ
(1) 2つのグループに分かれ、予算1,000万円(工事費込み)で設置できる遊具・ベンチ等を、カタログと計算機を手に選び、公園の図面に配置してみる。これが楽しくてワクワクだった。皆で使うものを、初めて私たち市民が選べるのだもの!
(2) 各グループの公園のレイアウト(案)を発表する。
 |
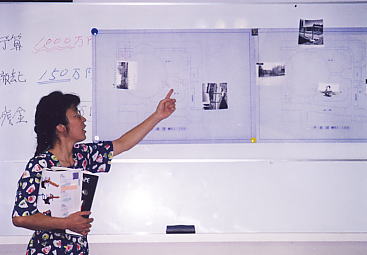 |
| 真剣そのもののお母さんたち |
発表にも熱がこもる |
3回目(7月22日)
(1) 2つの市民案をもとに、みどりのまちづくり課が1つの案にまとめ、それに対する意見を出し合い、最終案を練る。
(2) 「遊具を中心とした子どもたちのための視点だけでなく、高齢者や障害を持つ方をも視野に入れ、安らぎくつろげる公園にしてほしい。」との、高齢者からの意見も出され、工夫してベンチや日陰の植栽を増やす方向で検討することにする。
(3) 最終案を再度みどりのまちづくり課が細かい施工面から検討し、決定の結果については参加者に報告すると共に、公園に掲示することを約束する。
2回、3回目に参加した天田いづみの意見
- 水飲み及び手洗い場について現状1箇所を更に増やしたいとの皆の意見について、市内の公園で水飲み場が未設置の所も半数近くある中で、更に増やすことは市全体のバランスから見てどうなのか?
これに対しては、当初から考えてきたことでもあり、やはり増やしたいという方向になりました。予算の範囲内でのメニューであるので、これも一つの市民参加の結果といえましょう。「市全体のことも理解したうえで増やす判断をした。」そこが大事なところであると思います。
- ここで意見が反映されて終わりではなく、出来れば草を植える等、創る作業も出来ればよいが、せめて新しくなった公園に対し、何らかの参加をしていきたい。
「落ちているごみは拾う。手に負えないことは市に知らせ、危険があれば110番する。私は、もし毛虫がついて困ったら、取りにいきます。」
尚、バリアフリーについて今回は充分な議論には至らず、結果的にベビーカーや車椅子は入れない状況となっています。皆でより望ましいあり方を考えていきたいと思います。ご意見をお寄せ下さい。
 |
 |
| 改修された館第4児童公園 (2002.8) |
市民参加のまちづくり
みどりのまちづくり課では、1992年柏町の町内会に声をかけ、3回の打ち合わせを経て、1993年、地域住民の意見を反映したレインボーポケットパーク(ユリノキ通り富士見橋際)をつくりました。これが、志木市での住民参加型公園づくりの第一歩でした。
しかしながら、私自身、コンクリートで固めたあまり良くないイメージしか持ち得ませんでした。
1997年、豊島区や世田谷区の住民参加型まちづくりを見学し、議会でも提案してきました。
そんな中で、レインボーポケットパークについても、その参加のプロセス(進行過程)にこそ意味があったのだと思えるようになりました。
住まう私たちの意識改革にも時間がかかります。だからこそ、「やってみること」は重要です。
今回参加した皆は「私たちの声が反映されてよかった。」と満足そう。様々な人たちの立場や、全体を考えて譲り合うことの大切さも学びました。きっと、愛着のもてる公園に育てていかれるでしょう。
更なる市民参加を、市民の意志とパワーで実現していきましょう !!
(1999年8月)
トップページへ まちづくりの目次へ