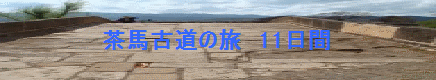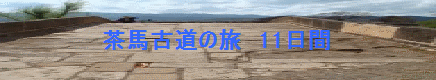Day(4):3月28日(日)
前日のお茶の飲みすぎで、睡眠不足で少々食欲もナシで、今朝の朝食はパス。
一泊朝食付きといっても、このホテルにはそんな設備も無く、ホテルの近くのロ-カルのお店で麺類を
食べるのです。
麺類は殆どス-プの麺ですが、味付けはナシで、お店に並んでいる、日本では見られない様な
薬味系を入れて、自分で味を調節します。
この麺には、前日、Kさんも少々食傷気味でしたが、今朝は違うお店で、少し味を濃くして食べ、
美味しかったそうです。
 午前8時、ガイドさんと共に、出発。
まず訪れたのは、孟海の「茶葉科学研究所」。 午前8時、ガイドさんと共に、出発。
まず訪れたのは、孟海の「茶葉科学研究所」。
  (茶経を書いた”陸羽”の銅像前で)
(茶経を書いた”陸羽”の銅像前で)
此処は、お茶についていろいろ研究しているところで、特に”紫目茶”に力を入れて要る様です。
”紫目茶”は、古茶の事で、コレステロ-ルを下げる効用が多いとの事です。
Day(2)、プ-ア-ルの「中国プ-ア-ル茶研究院」でも試飲したのですが、朝鮮にんじんの様な、
何か少々薬草の味がしました。
プ-ア-ルの研究院よりか、こちら、孟海の方が、紫目茶の研究は古く、積み方も一芯一葉で、
茶葉も良いそうです。
私は体に良いと言われると、すぐに好きになるタイプですが、そんな意味で、OKでした。
何度も試飲させていただき、体の中がきれいになる気がしました。
只、100g15,000円もするので、購入は。。。。。
 
(紫目茶の木) (真さに紫色です)

(弁護士モトムラ氏似?の先生&代表の方)
 次に訪れたのは、車で約4時間のプ-ラン族の住むプ-ラン山へ。
プ-ラン族とは、シ-サンパンナ暮らす少数民族の一つで、最も早くからお茶の栽培を始めたとされています。
現在では、約8万人が1200メ-トルの山岳地帯に暮らしています。 次に訪れたのは、車で約4時間のプ-ラン族の住むプ-ラン山へ。
プ-ラン族とは、シ-サンパンナ暮らす少数民族の一つで、最も早くからお茶の栽培を始めたとされています。
現在では、約8万人が1200メ-トルの山岳地帯に暮らしています。


(春、出産ブ-ムです。大きなお腹の黒豚のお母さん)
 
ここには、昔から”酸茶”と呼ばれるお茶があります。
”酸茶”とは、食べるお茶の事で、炒ったお茶を竹筒にいれ、数ヶ月土中に埋め、
発酵させそれを食べるのです。
自然崇拝の民族で、身近に採れるお茶を、おかずの様に食べるのは、生活の知恵でしょうか?
訪れた家の人の話では、今の若い世代の人は食べず、彼らのおばぁちゃんが食べていたそうです。
50歳でおばぁちゃんと言う女性が、私達の為に、作り方のデモンストレ-ションをしてくれました。

①茶葉を熱湯の中に入れる

②色が変わるまで混ぜる

③竹筒に詰め、粘土、椰子の葉で蓋をする

④数ヵ月後、土の中より取り出す

実際、頂いたのは、土の中に数ヶ月埋めていた物です。
少しの酸味と苦味を感じました。
おばぁチャンの時代には、男の煙草と同じで、くちゃくちゃとかみ、楽しんでいたのでしょうか?
他の民族に比べ、プ-ラン族の人々の生活は大変質素で、家の中は生活する最小必要品しか在りません。
戦前以上前の日本の田舎の生活が、時を越えて、そのまま続いているようでした。
お手洗いをお借りしたのですが、想像以上で・・・・kさんは「ウルルンの世界や!!」と叫んでいました。
その次は私のリクエストで、”竹筒茶”を愛用する、ハニ族の村に行きました。
”竹筒茶”は狩猟、採集を生業にしていた、ハニ族、ラフ族が伝えるお茶です。
ハニ族は現在約25万人で、主に1500メ-トルの山岳地帯に住んでいます。
”竹筒茶”を作ってくれたのは、ハニ族のラトウ氏、45歳。
山から切り出した青竹に水を入れ、沸騰したところで、焼いた茶の葉を入れ、1分くらい煮立て作ります。
出来上がったお茶は、青竹の香りがほんのりとし、香ばしく、ほうじ茶の様な味がしました。


それから、もう一つの”竹筒茶”の作り方とは・・
①5分程火であぶった青竹に散茶を詰めこみ、バナナの葉で蓋をし、3,4分火であぶる。
②とんとんとして、4,5回に分け、散茶を竹筒に一杯になるまで詰める
③最後に5分程火にかけ、棒で3回ほど付く
④出来上がった竹筒茶を10分ほど冷まして、斧で割る
竹から出る水分で茶葉が蒸され、棒で突く事により固められ、お茶が出来るのです。
プ-ア-ル茶の作り方と同じで、何年か置くと発酵が重ねられ、まろやかな美味しいお茶が出来上がるのです。
  

ラトウさんは、こうして昔からの方法でお茶を作り、家族用として飲み、又多くできると
売るそうです。一般には、樹齢300年の古い茶木より作るそうです。
前日行った“巴達”の茶樹王もあることだし、この辺には、こうして自然の古い茶木が多いのでしょう。
自然界からのすばらしい贈り物ですね。
茶馬古道を通り、東南アジア、チベットに運ばれるお茶の他に、地元の人々に根付ていた
お茶があったのですね。飲茶の習慣は、はるか太古の昔から・・・・すごいです!!
デモンストレ-ションで使った竹筒を捨てようとするので、私頂きました。
ついでに、その時のお茶も。
世界に一つの、ラトウさんオリジナルのお茶セットです。
何年か先に、円熟味を増したお茶を、旅の思い出と共に頂きましょう。
その後車で山を下り、南ジュ山の樹齢800年の古茶樹を見学の予定でしたが、
雨が降った為霧が濃く、断念しました。
 
(樹齢300年の茶樹) (ハニ族の子供達)

(茶摘を終わった、若いファミ-リ-と)

(大きい茶葉)

後、今宵の宿がある景洪(ジンホン)に向かいます。
本当にいたるところが茶畑になっています。まるで、緑に輝くジュ-タンです。
民族衣装を着て、茶摘をする彼女、笑顔がステキです。


|